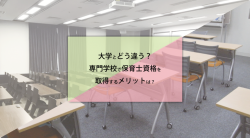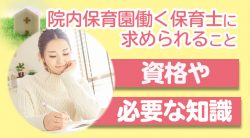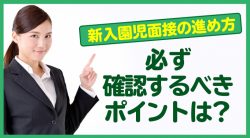月齢が上がってくれば保育士の話す簡単な言葉を理解し単語も少しずつ出てきますが、「〇〇をして遊びましょうね」「はーい!」というようなやり取りはまだできません。
また月齢による発達の差が大きい時期ですので、ねんねの赤ちゃんとお座りやハイハイができるようになった赤ちゃん、簡単な単語が話せるようになってきた子どもなど、発達によってコミュニケーションのとり方が違うことも特徴です。
そんな0歳児クラスでどのように子ども達とコミュニケーションをとれば良いのか、発達の違いごとに見ていきましょう。
ねんねの赤ちゃんとのコミュニケーションのとり方
一般的に赤ちゃんは、産まれたばかりのねんねの状態から、5ヶ月くらいまでに寝返りができるようになります。
そして、2,3カ月くらいから大人の顔をじっと見つめて笑ったり、声掛けに反応するようになり、4,5ヶ月頃からは「あーうー」と言った赤ちゃん特有の「喃語」を話すようになります。
ただ、どの発達も個人差がありますので、5ヶ月を過ぎても寝返りをしない場合もありますし、喃語を発するのがもっと早い場合や反対に遅い赤ちゃんもいてそれぞれです。そのため月齢差はもちろんですが、赤ちゃん1人ひとりに合わせたコミュニケーションが必要です。
まだ喃語が出ていない時期には、大人が1人で話かけているような気持になることもありますが、赤ちゃんにはしっかりと聞こえていますので、どんどん声をかけたり歌をうたってあげましょう。
その時のポイントは、赤ちゃんに笑顔を向けながら手を握ったりと、ふれあいも持つことです。赤ちゃんはどんな表情よりも無表情が苦手です。無表情に恐怖心を抱き泣き出してしまうことも…。優しい笑顔でゆっくりとコミュニケーションをとってみてくださいね。
喃語が出てきたら、赤ちゃんの喃語を「そうなの」「うんうん」と聞いてあげましょう。もちろん何を言いたいかはわかりませんが、時には保育士の声掛けに喃語で答えてくれることもありますよ。これが言葉でのやりとりの第一歩です。
ハイハイ、お座りの時期の赤ちゃんとのコミュニケーションのとり方
ハイハイやお座りができるようになると、視野が広がり様々なものに興味を持つようになります。大人の仕草を真似たり、お気に入りのおもちゃに手を伸ばすようになるのもこの時期ですね。
興味が広がるとコミュニケーションの幅もぐっと広がります。例えば、お座りができた様子を見て大人が「上手だね」と手をたたくと、それを真似て一緒に手をたたいたり、ハイハイで移動する時に「バイバイ」と手を振ると手を振り返してくれたりと、仕草でのコミュニケーションがしっかりととれるようになります。
その他にも、おもちゃを「どうぞ」と手渡すとお辞儀をしたり、登園時に「おはよう」と声をかけるとハイハイで保育士のもとまで来てくれたりと、保育士の話す簡単な言葉を理解していることもわかります。
大人の仕草を真似ることはコミュニケーションの第一歩ですので、何度でも繰り返し楽しみたいコミュニケーションの方法です。
簡単な単語を発するようになった子どもとのコミュニケーション
1歳から1歳半くらいになると、「ママ」「マンマ」「ワンワン」「ブーブ」など、簡単な意味のある単語を発するようになります。0歳児クラスでは、お誕生日を迎えて1歳になる子ども達もいますので、年度終わりが近付くにつれて単語を発することができる子どもも増えていきますね。
そんな時期の子どもとは、言葉でのコミュニケーションをたくさんとるようにしましょう。お散歩中には、「ワンワンいたね」「ブーブあったね」「電車だね。がたんごとんだよ」など子どもが理解しやすい擬音語での話しかけで、子どもの言葉は飛躍的に増えていきます。
また、大人の話すことを理解しできるようにもなってきますので、「どうぞ」と子どもにおもちゃを手渡し「ちょうだいな」と言っておもちゃを受け取るという一方通行ではないやりとりも楽しめるようになります。お友達との関りにも役立ちますので、言葉と行動でのやりとりはどんどん取り入れていきましょう。
自分の好きな遊びやおもちゃもはっきりとしてきますので、「どのおもちゃが良いかな?」
「どの絵本が読みたい?」とやりたいことを子どもに選んでもらうことも大切なコミュニケーションの1つです。
人との関わり方や自分の気持ちを相手に伝えることを学ぶ第一歩ですので、子どもの反応を見ながら関わってみてくださいね。
まとめ
コミュニケーションがとりづらいと思われがちな0歳児クラス。しかし、1人ひとりの発達を把握して、その時にどんな部分が育ってほしいかということを考えると、より良いコミュニケーションの方法が見つかります。
こども園から小規模保育園に転職したい!0,1,2歳児の保育に必要なこと