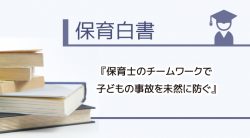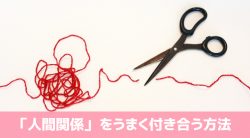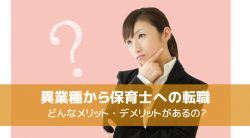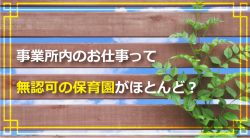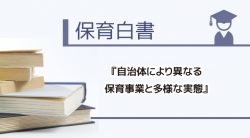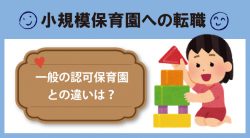見守るべきケンカ
人との関わり方を学ぶ上では、友達とのケンカは貴重な経験です。自分の思いを分かってもらう為に言葉で伝えようと努力し、相手の思いを受け止める事で我慢をするという過程も学びます。自分達でトラブルを解決するという経験は子どもの成長にとって大切な学びとなるのです。しかし、いつでも子どもに任せていれば良いのかというと、そういう訳ではありません。
まずは子ども同士でのケンカが始まったら、すぐに止められる場所で見守りましょう。叩く、引っ掻く、噛みつくなど怪我に繋がるようなトラブルに発展した際に、すぐに止められる様にする為です。言葉での言い合いの場合には、仲裁には入らずに傍で見守ります。お互いの主張を客観的に聞いていてあげてくださいね。
そのまま保育士が入らずに子ども同士で解決できたとしたら、子どもはまた1つ、人との関り方を学んで成長したのです。時には、周りの子どもが仲裁に入ろうとする場合もあるかと思います。そんな時も、保育士は傍で見守ります。しかし、一方の子どものみを皆で悪者にするような流れになってしまった時には、間に入ってあげて下さいね。その為にも、子ども達の様子を注意深く見守る必要があります。
仲裁に入るべきケンカ
すぐに仲裁にはいるべきケンカは怪我に繋がるケンカです。保育園は子どもを安全に預かるという役割がありますので、叩く、押す、引っ掻く、噛みつく、物を投げるなど怪我に繋がる様な行動をした時には、まずは子どもの動きを制止しましょう。手を掴んで止めようとすると、脱臼する恐れがありますので全身を抱きとめて制止する事をおすすめします。
落ち着いてからそれぞれの言い分を聞き、子どもの気持ちを受け止めた上で相手の気持ちも伝えてあげてください。手を出した方が一方的に悪いという仲裁はしないでくださいね。
少し見守った後に仲裁に入るべきケンカもあります。年齢が低いうちには特に、どうしてケンカをしているのかが分からなくなってしまい、ただ怒ったり泣いたり…という状況になりがちです。そんな時には、保育士が仲裁に入って気持ちを代弁してあげましょう。保育士が言葉にしてあげることで、落ち着いて自分の思いを伝えられる様になりますよ。
子ども同士のケンカで怪我をしてしまった時には
どんなに気を付けて見ていても、トラブルに気が付かずに怪我が起きてしまうという恐れもあります。そんな時には、まずは怪我の対応です。そして、落ち着いてからお互いの言い分を聞いてあげてください。怪我をさせた子どもが悪いという言い方にならない様な配慮が必要となります。その上で、「手を出すのではなく言葉で伝えてね」ということはしっかりと伝える様にしましょう。
保育中の怪我は保育園の責任となりますので、怪我をしてしまった子どもの保護者には相手の子どもの名前は伝えません。謝罪と状況説明を丁寧に行いましょう。
怪我をさせてしまった子どもの保護者に伝えるかということは、園の判断によって違います。その時だけではなく、トラブルになるといつも手が出てしまうという場合は、自宅での様子を伺うという意味でも伝える事もあります。しかしあくまでも園の判断になりますので、園長や主任に相談をしましょう。